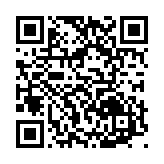2012年09月25日
大牟田市徘徊SOSネットワーク模擬訓練に参加してきました。
平成24年9月23日(日)に
大牟田市において、今回で第9回目となる「徘徊模擬訓練」が全市で行われました。
徘徊模擬訓練の究極の目的は「地域づくり」ですが、
その背景として、認知症の高齢者の方が徘徊して見つからず亡くなったという
ケースなどもあり、
認知症になっても安心して暮らせるまちを作るために
①市民への認知症の理解と見守りの重要性を啓発し、
②日常的な声かけ・見守りの意識を高めるとともに、
③徘徊行方不明発生時のSOSネットワーク構築を目的としています。
今回、視察当日の様子になどについてご報告いたします。
大牟田市役所に到着後、視察先の拠点施設へ振り分けられました。

●拠点施設の一つです。
ここは、市営住宅の1階に小規模多機能型居宅介護という施設が入っており、そこの
地域交流ホールが集合場所です。
のぼりを立ててイベント的な様子でした。
大牟田市では、小学校区ごとにこういった地域福祉の活動拠点が設置され、小規模多機能施設に
併設されています。全部で22校区あります。
9時に訓練がスタートし、警察より徘徊者の情報が関係機関に流され、
次に、市役所から愛情ネット(Eメールによる情報伝達システム)を通して各地区の主な方々や
拠点施設等やメール登録者などに流され、その情報を拠点施設から校区内のネットワークのメンバーへと
流されていきます。
連絡が入った地域の方は、拠点施設に駆けつけ、情報シートを受け取り
自分がどこの地域を探すかを準備されている地図に名前入りマグネットをはりつけます。
必ず、二、三人一組で捜索に出かけます。
なお、捜索時間は1時間半若しくは22時で終了ということになっていました。
情報シートは個人情報なので厳重に管理されています。
9時15分ごろに、ある程度人が集まって、捜索を開始しました。
私は、民生委員会長さんとPTA会長さんに同行させていただきました。
<いったん集合して、ミーティング>


徘徊者を探しています。
今回の訓練では、市内全域を対象として本物の徘徊者(もちろん訓練のです)とダミーの
徘徊者(本物とそっくりの格好をしてもらった方)が数名いらっしゃいました。
創作中に、情報シートに書いてある方とそっくりの方がおられ、
民生委員さんがすばやくその方に気づかれて、はじめ反対側の歩道を歩かれていたので、
急いで、横断歩道を渡って、徘徊者の前方に出て、PTA会長さんが
やさしく、声かけを「こんにちわ、○○さんですか?」とされました。
しかし、本物の方ではなく、ダミーの方でした。
民生委員さんからは、ダミーの方がおられることで声かけの訓練になることを教えていただきました。

その後、10時30分ごろまで捜索を行い、拠点施設に帰ってきました。
途中、民生委員さんが宅配業者の方や近所の方にイベントの説明と普及啓発活動を
行われていました。
終了後は、反省会を拠点施設で行いました。
反省会の後は、事務局の反省会と実施状況の説明会に伺い、
午後2時からは視察プレゼンテーションが行われ、
大谷るみ子先生からご講義を受けました。
今回の視察では地域づくりのための仕掛けや認知症への対策の取組み
地域や関係機関や行政が一丸となって取り組んでいる姿が良かったです。
更には、周辺市町村と協定を結んで、広域の協議会も立ち上がっているとの事でした。
大牟田市において、今回で第9回目となる「徘徊模擬訓練」が全市で行われました。
徘徊模擬訓練の究極の目的は「地域づくり」ですが、
その背景として、認知症の高齢者の方が徘徊して見つからず亡くなったという
ケースなどもあり、
認知症になっても安心して暮らせるまちを作るために
①市民への認知症の理解と見守りの重要性を啓発し、
②日常的な声かけ・見守りの意識を高めるとともに、
③徘徊行方不明発生時のSOSネットワーク構築を目的としています。
今回、視察当日の様子になどについてご報告いたします。
大牟田市役所に到着後、視察先の拠点施設へ振り分けられました。

●拠点施設の一つです。
ここは、市営住宅の1階に小規模多機能型居宅介護という施設が入っており、そこの
地域交流ホールが集合場所です。
のぼりを立ててイベント的な様子でした。
大牟田市では、小学校区ごとにこういった地域福祉の活動拠点が設置され、小規模多機能施設に
併設されています。全部で22校区あります。
9時に訓練がスタートし、警察より徘徊者の情報が関係機関に流され、
次に、市役所から愛情ネット(Eメールによる情報伝達システム)を通して各地区の主な方々や
拠点施設等やメール登録者などに流され、その情報を拠点施設から校区内のネットワークのメンバーへと
流されていきます。
連絡が入った地域の方は、拠点施設に駆けつけ、情報シートを受け取り
自分がどこの地域を探すかを準備されている地図に名前入りマグネットをはりつけます。
必ず、二、三人一組で捜索に出かけます。
なお、捜索時間は1時間半若しくは22時で終了ということになっていました。
情報シートは個人情報なので厳重に管理されています。
9時15分ごろに、ある程度人が集まって、捜索を開始しました。
私は、民生委員会長さんとPTA会長さんに同行させていただきました。
<いったん集合して、ミーティング>


徘徊者を探しています。
今回の訓練では、市内全域を対象として本物の徘徊者(もちろん訓練のです)とダミーの
徘徊者(本物とそっくりの格好をしてもらった方)が数名いらっしゃいました。
創作中に、情報シートに書いてある方とそっくりの方がおられ、
民生委員さんがすばやくその方に気づかれて、はじめ反対側の歩道を歩かれていたので、
急いで、横断歩道を渡って、徘徊者の前方に出て、PTA会長さんが
やさしく、声かけを「こんにちわ、○○さんですか?」とされました。
しかし、本物の方ではなく、ダミーの方でした。
民生委員さんからは、ダミーの方がおられることで声かけの訓練になることを教えていただきました。

その後、10時30分ごろまで捜索を行い、拠点施設に帰ってきました。
途中、民生委員さんが宅配業者の方や近所の方にイベントの説明と普及啓発活動を
行われていました。
終了後は、反省会を拠点施設で行いました。
反省会の後は、事務局の反省会と実施状況の説明会に伺い、
午後2時からは視察プレゼンテーションが行われ、
大谷るみ子先生からご講義を受けました。
今回の視察では地域づくりのための仕掛けや認知症への対策の取組み
地域や関係機関や行政が一丸となって取り組んでいる姿が良かったです。
更には、周辺市町村と協定を結んで、広域の協議会も立ち上がっているとの事でした。
Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at
14:36
│Comments(0)
2012年09月25日
パソコン教室(ひとりぐらし高齢者等安心ネットワーク構築事業)
今回、第2期の後半のパソコン教室が開催されました。

18名の方が参加され、2時間という時間があっという間でした。
本日は、約1ヶ月前の復習と本題であるインターネットの学習をしていただきました。

皆さん、思い思いにご自分の興味のあるものを検索されて
調べ物をされたり、ニュースをご覧になったりと楽しまれていました。
いよいよ、明日はメールの操作です。
メールができるようになるといろんな方にメッセージを送ることができるようになり
楽しみが広がります。
そして、それが見守り隊の活動につながっていくと確信しています。
それでは、皆さん、明日も頑張りましょう!

18名の方が参加され、2時間という時間があっという間でした。
本日は、約1ヶ月前の復習と本題であるインターネットの学習をしていただきました。

皆さん、思い思いにご自分の興味のあるものを検索されて
調べ物をされたり、ニュースをご覧になったりと楽しまれていました。
いよいよ、明日はメールの操作です。
メールができるようになるといろんな方にメッセージを送ることができるようになり
楽しみが広がります。
そして、それが見守り隊の活動につながっていくと確信しています。
それでは、皆さん、明日も頑張りましょう!
Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at
13:05
│Comments(0)
2012年09月14日
介護になる状態を予防するための取組み
今日は、介護になる状態を予防するための取組みについてお知らせします。
具体的に個々人で何をするかという、例えば、身体を動かすとか趣味を持つ
等については今回はお知らせせずに、行政の取組みと地域包括支援センター
の具体的な動きについてお知らせします。
平成24年度の介護保険の改正で、地域包括ケアシステムの構築を2025年までに
行うということがあげられています。
ここで、地域包括ケアシステムという言葉となぜ、そのシステムを2025年までに
作り上げなければならないのかという疑問が出てくるかと思います。
まず、地域包括ケアシステムですが「住み慣れた地域で」できるだけ長く元気で
自分でできることは自分で行うために、介護が必要になる状態をできるだけ遅らせる
ために必要な予防や介護や医療や生活支援サービスや住宅のサービスを必要に応じて
組み合わせて提供するシステムです。

2025年というのは、団塊の世代の方々が、75歳になる年です。
2015年に団塊の世代の方々が65歳になり、いわゆる高齢者になり、
2025年には介護リスクの高い後期高齢者になるので、そのためのシステムを
今のうちから構築していこうというものです。
このシステムのコーディネート機関として位置づけられているのが
地域包括支援センターです。
2006年の介護保険の改正で地域包括支援センターができ、その機能強化を
図るべくさまざまな事業が取り組まれています。
そのうちのいくつかを紹介します。
まず、地域ケア会議です。これは、地域包括支援センターの職員やケアマネジャーが
作成する介護予防支援計画書(予防ケアプラン)を利用者の自立に向けた方向性を示す
ものとするために、行政や地域包括支援センターや専門職(リハビリ専門職、管理栄養士、
歯科衛生士)や介護予防サービス提供事業所が集まり行われる会議です。
結局、その会議でそうそうたるメンバーが集まり、何をするかというと、
ケアマネジャーなどが立てた予防ケアプランが利用者本人の自立を促すものになっているか、
自立できたら、サービスから卒業するようにすることを話し合う会議です。
利用者本人ができにくいことを期限を決めてできるようにして、
できるようになれば、介護保険サービスからの卒業ということになります。
たとえば、さて、将来像1,2を見てどちらが、利用者本人の自立になっていますか?また、年をとってもどちらを望まれますか?
年をとっても、人のお世話にならず、身の回りのことができるといいですね。
具体的に個々人で何をするかという、例えば、身体を動かすとか趣味を持つ
等については今回はお知らせせずに、行政の取組みと地域包括支援センター
の具体的な動きについてお知らせします。
平成24年度の介護保険の改正で、地域包括ケアシステムの構築を2025年までに
行うということがあげられています。
ここで、地域包括ケアシステムという言葉となぜ、そのシステムを2025年までに
作り上げなければならないのかという疑問が出てくるかと思います。
まず、地域包括ケアシステムですが「住み慣れた地域で」できるだけ長く元気で
自分でできることは自分で行うために、介護が必要になる状態をできるだけ遅らせる
ために必要な予防や介護や医療や生活支援サービスや住宅のサービスを必要に応じて
組み合わせて提供するシステムです。

2025年というのは、団塊の世代の方々が、75歳になる年です。
2015年に団塊の世代の方々が65歳になり、いわゆる高齢者になり、
2025年には介護リスクの高い後期高齢者になるので、そのためのシステムを
今のうちから構築していこうというものです。
このシステムのコーディネート機関として位置づけられているのが
地域包括支援センターです。
2006年の介護保険の改正で地域包括支援センターができ、その機能強化を
図るべくさまざまな事業が取り組まれています。
そのうちのいくつかを紹介します。
まず、地域ケア会議です。これは、地域包括支援センターの職員やケアマネジャーが
作成する介護予防支援計画書(予防ケアプラン)を利用者の自立に向けた方向性を示す
ものとするために、行政や地域包括支援センターや専門職(リハビリ専門職、管理栄養士、
歯科衛生士)や介護予防サービス提供事業所が集まり行われる会議です。
結局、その会議でそうそうたるメンバーが集まり、何をするかというと、
ケアマネジャーなどが立てた予防ケアプランが利用者本人の自立を促すものになっているか、
自立できたら、サービスから卒業するようにすることを話し合う会議です。
利用者本人ができにくいことを期限を決めてできるようにして、
できるようになれば、介護保険サービスからの卒業ということになります。
たとえば、
現在 Aさん 掃除
・お風呂の掃除が出来ないのでヘルパーを利用したい。
将来像1
・自分は、お風呂掃除は入浴後に浴槽から出ないで水を流し、そのままスポンジで軽くこする事にした。
週2回はとっての長いスポンジで屈まずにこすることできれいになることをヘルパーと一緒に練習して確認できた。
・お風呂の掃除が出来ないのでヘルパーを利用したい。
将来像1
・自分は、お風呂掃除は入浴後に浴槽から出ないで水を流し、そのままスポンジで軽くこする事にした。
週2回はとっての長いスポンジで屈まずにこすることできれいになることをヘルパーと一緒に練習して確認できた。
将来像2
・今まで室内の掃除機かけはしていたがヘルパーが来るときにお願いするからしなくなった。
これからもヘルパーさんにお願いして掃除は自分ではもう歳だから出来ないと思う。
・今まで室内の掃除機かけはしていたがヘルパーが来るときにお願いするからしなくなった。
これからもヘルパーさんにお願いして掃除は自分ではもう歳だから出来ないと思う。
年をとっても、人のお世話にならず、身の回りのことができるといいですね。
Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at
14:47
│Comments(1)
2012年09月11日
モデル事業の主な経過報告と思うこと。
ひとり暮らし高齢者安心ネットワーク構築事業が平成23年7月に始まり、
1年と2ヶ月が経過しました。
平成25年3月までのモデル事業となっています。
平成23年度にはニーズ把握などのためにアンケート調査を実施させていただき、
それに基づき、今年度はひとり暮らしの方をどのように見守っていく体制を
構築すべきか、事業を行っています。
現在、取り組んでいるものは主に4つあります。
1、地域の福祉組織の中に入って、ひとり暮らし高齢者等を見守るために
どのようなネットワークや体制が必要かについて地域の方々とともに
検討しています。
地域にあるさまざまな組織団体による直接的な見守り(民生委員さんの訪問や
老人会による友愛訪問など)や間接的な見守り(さまざまな活動や会合に
定期的に参加することで、元気かどうか確認できる)が行われている。
これらのネットワーク化を行うことで有機的な見守りが実現できると思われる。
その要になるのが、地域福祉計画及び活動計画で結成された地域福祉組織と
思われますので、地域包括支援センターもその中で社会資源の一つとして
専門性を発揮していきたいと思います。
2、民間事業者にご協力いただき、見守りネットワークの幅や厚さを大きくしていきます。
ライフラインを中心とした事業所や地域をくまなく回っている事業所の方々に
この事業の説明を行い、ひとり暮らし高齢者の見守りへのご理解とご協力を
いただくように取り組んでいます。
しかし、課題がいくつかあり、個人情報の取り扱いや見守ってほしい人や
かかわりも持ちたくない人の区分け等があります。
3、郵便による見守り事業
平成24年2月から実験的にはじめ、4月から担当校区で本格実施しています。
昨年度のアンケートで、郵送による情報提供や安否確認お元気確認票」)
を双方向でやり取りができるようにしています。
この郵送による見守りや情報提供は、アンケートの中で一番希望が多かったものです。
約300人の方とやり取りをしていますが、お元気確認票に最近の生活やお体の状況を
書いていただいている方も居られ、それに対してお返事を次回の郵送時に書いて
お送りさせていただいています。
4、パソコン教室
Eメールを見守りの手段として活用しようというものです。
地域のひとり暮らしの方などで、最近見ないとか、新聞がたまっている、
回覧板が何日もおきっぱなしになっているなどの状況が起こったときに、
Eメールを使って市役所や地域包括支援センターに連絡をしていただくものです。
また、地域包括支援センターからは、Eメールを使って医療や健康や介護や福祉
などについて登録者に情報提供を行う、双方向のシステムを構築しようとしています。
そのためには、65歳以上の多くの方にパソコンの使い方を学んでいただく(裾野を広げる)
機会を作りつつ、Eメールができるようになっていただく(質を高める)事の
両方を行っています。
現在は、モデル事業で4日コースを2回開催中ですが、定員いっぱいで、皆さん
たくさんのことを学んで帰っていただいております。
このモデル事業では、人の力による見守りだけでは限界があり、その限界点を上げて
効率的に見守りや情報発信ができるようにするためにはどうすればよいかということで
始まりました。
大分県はITを活用して行おうとしています。しかし、アンケート結果ではパソコンや携帯の
メール機能を使って見守りができるための下地さえも不十分でした。
よって、中津においては、上記しましたが、裾野を広げるための取り組み(パソコン教室)と
質を高めるための取り組みを同時並行的に行っていく必要があると考えています。
出張パソコン教室も今後大きく展開したいと思います。
経費が余りかからず、持続可能なモデルが何なのかを考えながら今後も取り組んで行きます。
一方で、見守りの方法が多チャンネルであってもいいと思いますので、希望の多い郵送も
絡めて考えて行きたいと思います。
1年と2ヶ月が経過しました。
平成25年3月までのモデル事業となっています。
平成23年度にはニーズ把握などのためにアンケート調査を実施させていただき、
それに基づき、今年度はひとり暮らしの方をどのように見守っていく体制を
構築すべきか、事業を行っています。
現在、取り組んでいるものは主に4つあります。
1、地域の福祉組織の中に入って、ひとり暮らし高齢者等を見守るために
どのようなネットワークや体制が必要かについて地域の方々とともに
検討しています。
地域にあるさまざまな組織団体による直接的な見守り(民生委員さんの訪問や
老人会による友愛訪問など)や間接的な見守り(さまざまな活動や会合に
定期的に参加することで、元気かどうか確認できる)が行われている。
これらのネットワーク化を行うことで有機的な見守りが実現できると思われる。
その要になるのが、地域福祉計画及び活動計画で結成された地域福祉組織と
思われますので、地域包括支援センターもその中で社会資源の一つとして
専門性を発揮していきたいと思います。
2、民間事業者にご協力いただき、見守りネットワークの幅や厚さを大きくしていきます。
ライフラインを中心とした事業所や地域をくまなく回っている事業所の方々に
この事業の説明を行い、ひとり暮らし高齢者の見守りへのご理解とご協力を
いただくように取り組んでいます。
しかし、課題がいくつかあり、個人情報の取り扱いや見守ってほしい人や
かかわりも持ちたくない人の区分け等があります。
3、郵便による見守り事業
平成24年2月から実験的にはじめ、4月から担当校区で本格実施しています。
昨年度のアンケートで、郵送による情報提供や安否確認お元気確認票」)
を双方向でやり取りができるようにしています。
この郵送による見守りや情報提供は、アンケートの中で一番希望が多かったものです。
約300人の方とやり取りをしていますが、お元気確認票に最近の生活やお体の状況を
書いていただいている方も居られ、それに対してお返事を次回の郵送時に書いて
お送りさせていただいています。
4、パソコン教室
Eメールを見守りの手段として活用しようというものです。
地域のひとり暮らしの方などで、最近見ないとか、新聞がたまっている、
回覧板が何日もおきっぱなしになっているなどの状況が起こったときに、
Eメールを使って市役所や地域包括支援センターに連絡をしていただくものです。
また、地域包括支援センターからは、Eメールを使って医療や健康や介護や福祉
などについて登録者に情報提供を行う、双方向のシステムを構築しようとしています。
そのためには、65歳以上の多くの方にパソコンの使い方を学んでいただく(裾野を広げる)
機会を作りつつ、Eメールができるようになっていただく(質を高める)事の
両方を行っています。
現在は、モデル事業で4日コースを2回開催中ですが、定員いっぱいで、皆さん
たくさんのことを学んで帰っていただいております。
このモデル事業では、人の力による見守りだけでは限界があり、その限界点を上げて
効率的に見守りや情報発信ができるようにするためにはどうすればよいかということで
始まりました。
大分県はITを活用して行おうとしています。しかし、アンケート結果ではパソコンや携帯の
メール機能を使って見守りができるための下地さえも不十分でした。
よって、中津においては、上記しましたが、裾野を広げるための取り組み(パソコン教室)と
質を高めるための取り組みを同時並行的に行っていく必要があると考えています。
出張パソコン教室も今後大きく展開したいと思います。
経費が余りかからず、持続可能なモデルが何なのかを考えながら今後も取り組んで行きます。
一方で、見守りの方法が多チャンネルであってもいいと思いますので、希望の多い郵送も
絡めて考えて行きたいと思います。
Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at
11:24
│Comments(0)
2012年09月04日
パソコン教室(第1期後半)

9月4日の10時からパソコン教室がありました。
今回は二日間でインターネットとEメールを学んでいただき、
その結果、見守り隊として登録いただき、地域の見守り隊に
なってほしいなあと思っています。
皆さん真剣に、講師の方のお話を聞かれながら、
パソコン操作を一生懸命にされていました。
また、明日もあります。皆さん頑張ってください。
Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at
18:35
│Comments(0)
2012年09月04日
高齢者虐待対応研修を受けてきました。
去る、8月29日~31日まで、
大分県と大分県社会福祉士会の共催で
高齢者虐待対応研修がありました。
平成18年に施行されたいわゆる
高齢者虐待防止法に基づき、
行政の責任においてその対応を
行い、地域包括支援センターもその協力機関
として関わっています。
虐待対応に関する一連の流れや記録の仕方など
多面的に学びました。
虐待が発生しない地域になればいいなあと思います。
因みに、虐待は
身体的虐待
心理的虐待
介護放棄・放任(ネグレクト)
性的虐待
経済的虐待があります。
地域の中で、なにか変だな?虐待かも?
と思ったときは行政や地域包括支援センターに
ご相談いただきたいと思います。
大分県と大分県社会福祉士会の共催で
高齢者虐待対応研修がありました。
平成18年に施行されたいわゆる
高齢者虐待防止法に基づき、
行政の責任においてその対応を
行い、地域包括支援センターもその協力機関
として関わっています。
虐待対応に関する一連の流れや記録の仕方など
多面的に学びました。
虐待が発生しない地域になればいいなあと思います。
因みに、虐待は
身体的虐待
心理的虐待
介護放棄・放任(ネグレクト)
性的虐待
経済的虐待があります。
地域の中で、なにか変だな?虐待かも?
と思ったときは行政や地域包括支援センターに
ご相談いただきたいと思います。
Posted by 中津市地域包括支援センターいずみの園 at
18:23
│Comments(0)